【十八禁】箱庭 ~いわゆる純文学風短編小説~ 第一話【二話完結】

箱庭(はこにわ)は、小さな、あまり深くない箱の中に、小さな木や人形のほか、橋や船などの景観を構成する様々な要素のミニチュアを配して、庭園や名勝など絵画的な光景を模擬的に造り、楽しむものである。
Wikipaediaより抜粋引用
人々は、谷山修一と片野知美のカップルを『理想』だと口々に言い合っていた。
私もそれには同意であった。
本来、異議や異論がない場合、黙っているべきであり、わざわざ口を開いて言う必要はない。
私は常々、そう思っていた。
そういう意味で、世間は私にとってうるさすぎるのだ。
私が通っていたのは、市内でも常にトップを争う進学実績をあげる高校である。
旧制中学からの流れを汲み、百年以上の歴史を持った我が校は、質実剛健を校訓とした校風のせいか、それとも単に田舎であったせいか、男女交際には奥手な学生たちが多かった。
その中で、交際を隠そうとも否定しようともせず、明らかにしていた谷山・片野の両名はある種、珍しい存在であった。
普通なら嫉妬ややっかみから陰口がどこからともなく聞こえてくるものだが、学年一の美男と美女が付き合っていたからか、悪く言う者はいなかった。
もしかしたら、内心よく思っていない連中もいたかもしれない。
たとえば、両人に密かに憧れていた、少なくはない人数の男女である。
しかし、それが表に出てこないのは、彼・彼女に目立った欠点がなかったからだろうと私は分析していた。
二人が共に眉目秀麗、容姿端麗であることは周知の事実だ。
それでいて、両人とも闊達かつ温厚な性格で、誰とでも分け隔てなく接するのである。
また、揃って学業成績は常に学年上位であり、それぞれバスケ部とバレー部のキャプテンをしている。
しかも、互いに互いを信頼し尊重し合っているのか、四六時中行動を共にしているということもなく、学内では二言三言、言葉を交わす程度であった。
それがゆえ、彼らが交際していることを初めのうちは誰も気づかなかった。
発覚したのは、実に交際後三ヶ月以上経過してのことだったというのが定説となっていた。
真偽のほどは知らない。
二人は交際について、またお互いのことについて積極的にしゃべりたがらなかったからだ。
その態度がまた、二人の株を上げることになっているのだが、当人たちが意識してそうしていたのか窺い知るすべもない。
正に、理想の二人なのである。
私も、彼らが一緒にいるところを見ると、思わず見とれてしまうことがあった。
だから当然、誰もその間に割り込める者などいないだろうと思っていた。
あの時までは。
それは、三年生の夏の終わりのことであった。
夏の大会をもって、すべての部活動で三年生が引退する。
私自身は最後の大会となるインターハイ予選において、団体戦ではベスト16、個人戦100kg超級では準々決勝敗退という中途半端な結果を残し、引退した。
とはいえ、約一年間務めた名門柔道部の主将という重責を後輩に引き渡した時点で、肩の荷が下りた。
これ以降は大学受験に向け、勉強に励まなければならないのだが、三年生には最後のイベントが残っていた。
そう、体育祭である。
体育祭の運営自体は二年生が受け持つので、我々三年生がやるべきことは少なかった。
せいぜい男女別で行われるマスゲーム的なダンスの練習ぐらいなものである。
しかし、半強制で行われる夏期講習を受けた後に、暑い中、皆で集まって行うそれは何とも楽しいものであった。
そのように皆の気分が高揚している中、事件は起こった。
片野知美に言い寄る男が現れたのである。
言い寄ったとされる(私は噂で聞いただけで現場を見ていたわけではない)のは元サッカー部のエース、吉永という男であった。
隣りのクラスではあるが、彼も谷山修一と同様に女子生徒から人気があった。
一説によると、後輩を中心としてファンクラブなるものまで存在するようである。
吉永は、谷山修一とは違うタイプの人間であった。
谷山修一はどちらかというと寡黙であり、物腰が柔らかく、人当たりの良い男である。
一方、吉永は陽気かつ押しが強く、率直な性格の持ち主であるらしい。
片野知美に言い寄る男が現れたという話を聞いたとき、私の心にはさざ波が立った。
それが何だったのか正確に表現するのは難しい。
恋心からくる焦りとは呼べぬほど小さなものであったし、そもそも私は片野に恋をした覚えがない。
無意識にそれを封じ込めていたのかもしれないが、仔細に検討した結果、違うという判断を下した。
私はその夜、布団の中でまんじりともせず、考え続けた。
心に沸き立った『さざ波』が、芸術を冒涜する者に対する憤りに近いものだと気づいたのは、夜が明けようとしていた頃であった。
スポンサーリンク
早朝、私は制服に着替え、外へ出た。
学校の夏期講習が始まる時間にはまだ早いが、やるべきことがあった。
私は早めに登校し、独り自転車置き場の近くで待った。
吉永の通学手段は知らなかったが、出身中学から自宅の位置を推測し、自転車通学だろうと判断した。
果たして、その読みは当たったのである。
夏期講習が始まる五分ほど前に、吉永が校門から入って来たのが見えた。
自転車置き場の前に立った私の横を、半ば強引にすり抜けようとする。
私は、吉永の首に腕を巻きつけて自転車から引きずり下ろした。
「げえっ」
というガマガエルが踏みつぶされたような声をあげ、吉永が勢い良く背中から地面に落ちた。
とっさのことだったせいか、受け身が不十分だった。
自転車は少し進み、倒れたらしい。
それが誰にも危害を加えなかったことが、背後から聞こえた数人の声でわかった。
「痛っ」
一瞬、何が起こったのかわからないという表情の吉永だったが、すぐに事態をつかんだらしかった。
「てめぇ、何すんだよ」
吉永が猛然と私に食ってかかり、左手で私のカッターシャツの胸元をつかんだ。
見上げてくる吉永の目には、怒りと困惑の色が浮かんでいた。
「何とか言えや、コラ」
吉永が凄んだが、私は答えなかった。
次の刹那、吉永の目に浮かんだ害意を私は見逃さなかった。
自然と身体が動いた。
振り上げてくる右の拳をかわしながら、吉永の奥襟を右手でつかんで半身になり、脚を跳ね上げた。
内股。
きれいに決まった。
「ぐぼっ」
吉永が再び地面に叩きつけられる。
素人の吉永は、やはり受け身が下手だった。
束の間、息ができなかったのか盛大に咳き込み、荒い呼吸をしている。
先ほど自転車から落ちたときのあの体勢は、とっさのことに対応できなかったのではない。
吉永は修練不足なのである。
私はそう確信した。
非常時に対応できなければ、習ってきた武道の意味がない。
週一回の武道の時間に何をしていたのだと問いたかったが、吉永が剣道を選択していたことを思い出し、納得が行った。
「うがが」
情けないうめき声をあげる吉永に視線をやる。
どうやら立ちあがることができないらしい。
「てめぇ、何すんだよ、ボケ」
地面に倒れたままの吉永が、顔をしかめて悪態をついた。
圧倒的に不利な立場にある現状を把握していないのか、それを考えられないほど激情が心を占めているのかわからなかった。
いずれにせよ立場をわきまえない人間を、私は嫌いである。
吉永が、そんな嫌いな部類の人間であってよかったと、私は内心に胸を撫で下ろした。
「片野知美に言い寄るのをやめろ」
私は言った。
「ああ?」
吉永が絞り出すように言った。
精一杯の反抗らしかった。
私は吉永の身体をつかみ、無理矢理立たせた。
「片野知美に言い寄るのをやめろ」
同じ台詞を再度、言った。
私は、吉永の瞳の中に怯えを見て取った。



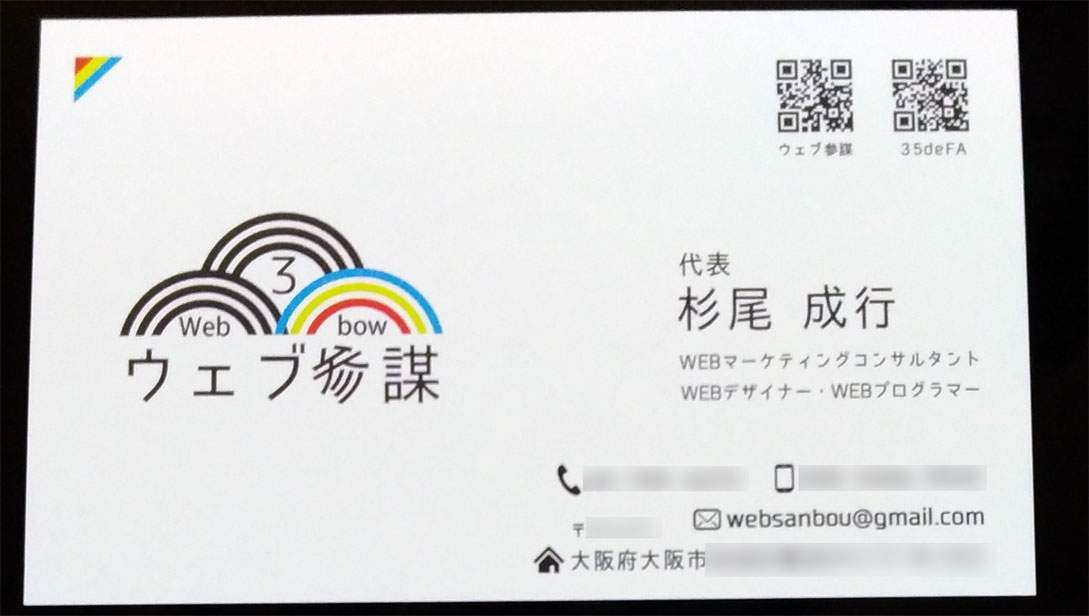



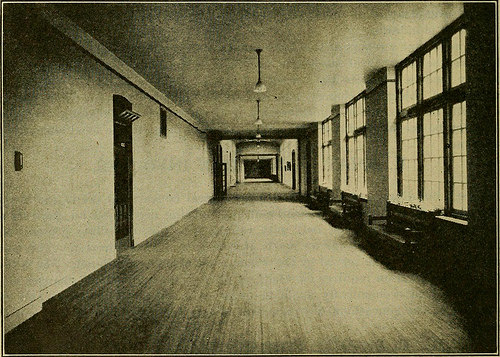
LEAVE A REPLY