【十八禁】箱庭 ~いわゆる純文学風短編小説~ 第二話【二話完結】
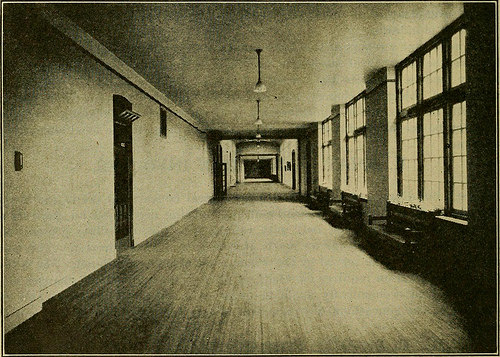
一話目はコチラ

私が吉永を脅したということは、その日のうちに噂として広まったようである。
吉永に忠告した後で気づいたが、遠巻きに人だかりができていたのだ。
それだけの人間が見ていたのであれば、無理もなかった。
次の日のことだった。
体育祭の練習を終え、帰宅しようと思っていた矢先、不意に背後から声をかけられた。
「前嶋」
私はその声を遠くのもののように聞きながら歩いた。
「ちょっと、無視しないでくれる?」
「あ…」
私は自分が呼ばれていることに、遅れて気づいた。
振り返ると、そこには隣りのクラスの横田恭子がいた。
数学の補習クラスで一緒であったため、彼女が硬式テニス部だったことを私は知っている。
そして、その横田恭子の背後に五人の女子学生がいた。
「前嶋。あんた、昨日、吉永君に暴力ふるったんだって?」
横田恭子が三白眼気味の目で、私を見上げて言った。
「え? あ、いや、まあ」
「はっきりしなさいよ」
横田恭子の後ろにいた、背の低い女子学生が金切り声をあげた。
どうやら、この面会が穏当なものになりそうにないということを、私は今更ながらに気づいた。
「答えて」
横田恭子がそう言って、真っ黒に日焼けした両腕をふくよかな胸の下で組んだ。
「事実だ」
私は言った。
「あんたさあ、『片野知美に手を出すな』とか言ってたらしいじゃん? どういうつもり?」
「え? 何?」
私はその質問の意図をはかりかねて聞き返した。
しかし、どうやらそれがよくなかったらしい。
「は? 『何?』じゃねぇよ。吉永君に暴力ふるった理由を聞いてんだよ」
別の女子学生が大声で言った。
「だったら最初からそう聞けばいいのでは?」
ついつい漏らした心の声が、彼女たちの激情を駆り立てたようである。
その後はさながら人民裁判であった。
いや、裁判ですらなかった。
それは言葉の正しい意味での『袋叩き』であった。
「あんたが何も答えないから聞いてんじゃん、馬鹿なの?」
「謝れよ。吉永君に謝れ」
「そんなデカい身体して弱い者いじめするなんてサイテー。マジサイテー」
「知美に聞いたら話したこともないって言うじゃん。どういうこと?」
「土下座、土下座」
「その目、何? 言いたいことがあったら言えば? キモイんだけど」
「聞いてんのかよ」
私的な興味が混ざっているようにも感じられたが、いずれにせよ私は聖徳太子ではないので即座に全員の質問及び要望には答えられない。
そもそもどういう理由で、彼女たちがわざわざ集まり、私を呼び止めたのかよくわからなかった。
私を糾弾したいのか、理由を説明してほしいのか、吉永に謝罪しに行け(もしくは一緒に行こう)ということなのか。
私は、皆目見当もつかない状態に陥っていたのである。
「吉永君に聞いたら、『知美に言い寄ったことなんてない』って言ってたけど。それについてはどう思ってるの?」
横田恭子の口から発せられた言葉に、私はと胸を突かれた。
それが事実であるのなら、私は錯誤を元に行動したことになる。
「一方の証言だけではわからない」
私は至極当然なことを答えた、つもりだった。
「はあ? 吉永君がそう言ってんだけど。吉永君を嘘つき呼ばわりするわけ?」
「マジキモイ」
「何、こいつ」
「人を殴った上で、嘘つき呼ばわりするなんてサイテー」
「ちょっとマジで意味がわかんないんだけど」
「知美とどういう関係? 片思い?」
「謝りもせずに。まじ野蛮人、ゴリラ」
「埒が明かない。警察に言った方が早くない?」
「それがよさそう」
横田恭子が同意したのをきっかけに、彼女たちは私に見向きもせずに行ってしまった。
彼女たちの後姿を見送りながら、私は理不尽に人権を蹂躙されたような気分になり、吐き気を覚えた。
結局、警察が私を訪れることはなかった。
数少ない知り合いから聞いたところによると、吉永が片野知美に言い寄ったかどうか真相はわかっていないらしい。
吉永は否定し、片野知美は沈黙を保っているということだった。
しかし、噂は独り歩きするもので、私が片野知美に恋をしている(これはくだんの女子学生も言っていた)とか、私が谷山修一に頼まれてやったという話まで出ているらしい。
更には谷山修一と片野知美の二人から頼まれたという説も一部では信じられているようだ、とも聞いた。
それらについて、忸怩たる思いがあったものの、私は特に抗弁しなかった。
というより、抗弁する相手もいなかった。
針の筵に座るとはこういうことを言うのであろうか。
それまで周囲は私に無関心だったのに、突如として奇異と敵意の視線が向けられるようになった。
そうなると、こちらとしても警戒せずにはいられない。
いつ何時、その敵意が害意に変わるやもしれないのだ。
私は警戒心をみなぎらせ、すれ違う者、近くにいる者に対して注意の眼差しを送る日々を過ごした。
表立って行動に出る者はいなかったものの、それで警戒を怠るわけにはいかなかった。
そういう不穏かつ不気味な状態にストレスを感じていたせいか、私は後頭部に痛みを覚えるようになり、また身体中に蕁麻疹が出た。
ときに頭を押さえ、ときに叩き、そして全身をかきむしった。
それでも学校にいる間は、耐え難い痛みと痒みが断続的に襲ってきた。
私は随分とそれらに苦しめられた。
だが、救いはあった。
谷山修一と片野知美。
どちらかを見るだけで私は癒され、その瞬間だけは頭痛も痒みも消え失せた。
ましてや二人が談笑しているところを見ると、私は心の深い部分で救われていると感じるのであった。
それは魂の救済と言い換えてもよいほど、私にとって根源的な癒しであり、欠くべからざるものになりつつあった。
彼、彼女は私にとって唯一絶対の存在だったのである。
しかし、あるとき、それは唐突に終焉を迎えることとなる。


それは啓示であったのかもしれない。
私はその日、いつもよりかなり早く目が覚めた。
柔道部の朝練があったときならいざ知らず、引退した今となっては早起きしても時間を持て余すだけである。
早朝の街は、空気が澄み切っているように感じられ、大層心地が良かった。
私は駅から学校までの道のりを、いつもと別の景色のように感じながらゆっくりと歩いた。
校舎にたどり着き、二階の窓から眺めると野球部の連中が元気良く掛け声を出し合い、練習に励んでいた。
恐らく柔道場でも、我が後輩たちが切磋琢磨していることであろう。
そんなことを思いながら、私は教室へ向かう前に用を足そうと、便所へ向かった。
便所は、一般棟と特別棟とをつなぐ渡り廊下の途中にある。
私は何の気なしにそこへ向かって歩き、手前にある男子便所へ入ろうとした。
そのときだった。
普段はそんなことはないにもかかわらず、私は特別棟に気を惹かれた。
渡り廊下と特別棟の間には、金属製のドアがある。
家庭科室や理科実験室などがある特別棟へ入るには、職員室にある鍵が必要だった。
私は、そのことを知っていた。
であるにもかかわらず、私は特別棟の方へ向かった。
何の気なしにドアノブに手をかける。
ドアの鍵が、開いていた。
ゆっくりと押し開ける。
特別棟に足を踏み入れた瞬間、それが当然であるかのように感じられた。
私は、鍵が開いていることを知っていたかのように、自然に振る舞う自分に内心驚いていた。
南側に教室があるせいで、特別棟の廊下は薄暗かった。
私は何かに引き寄せられるように、階段へ向かった。
そのとき、人の気配がした。
上階からだった。
身じろぎした音が聞こえたとか、声が聞こえたわけではなかった。
そこに人がいることが、ただ『わかった』。
私は暗い階段をゆっくりと登り始めた。
床から浮いているように足の感覚がなかった。
自分の息が荒くなるのを感じた。
それがなぜなのかわからなかった。
三階を過ぎ、四階にたどり着いたとき、耳朶を打つ音があった。
それは抑えた呼吸のような、一定の間隔で発せられる音だった。
この上は、屋上へ続く階段だった。
私はその階段に足をかけた。
そうしなければならないという使命感にも似た何かが私を突き動かしていた。
踊り場にたどり着き、方向を変えたとき、人の気配が変わったように感じられた。
音が聞こえなくなった。
私は手にしていた通学用バッグを放り投げ、階段を駆け上がった。


そこには、谷山修一と片野知美がいた。
階段の上、屋上へ入るためのドアの手前にある狭い空間。
彼と彼女は半裸で抱き合っていた。
谷山修一にいたっては、ズボンと下着を脱ぎ捨て下半身がむき出しになっていた。
片野知美が怯えたような、蔑んだような目で私を見ていた。
「ちょ、な…」
谷山修一が何かを言いかけた。
その瞬間、私は自分を律することができなくなった。
気づくと、谷山修一が顔面血だらけで倒れていた。
断片的に覚えているのは、私が谷山修一の顔を何度も殴りつけたこと、それから彼の背後をとって裸絞めにしたことだった。
絞めるポイントをずらしたせいで、すぐに谷山修一は失神したようだった。
「許せない、裏切りは」
私は自らのつぶやきを、遠いもののように聞いていた。
彼と彼女が、私を裏切ったことは明白であった。
二人は私の理想であり、理想の二人はこのような行為に及んではならない。
絶対に。
私たちの高校生活の理想を、二人が体現しなければならないのだ。
そこに、邪な気持ちがあってはならない。
二人が裏切ったのは、私だけではない。
少なからぬ数の男女が二人を理想と見なし、憧憬の念を持っているのだ。
理想の男女となった彼と彼女には、それを全うする義務がある。
このような行為をしてはならない。
決して許されることではないのである。
私はそれを説こうと谷山修一の上半身を起こし、背中を叩いた。
しかし、彼は目を覚まさなかった。
再度、背中を叩く。
が、結果は同じであった。
床に寝かし、彼の口元に耳を近づけた。
呼吸が停まっていた。
私はその光景が信じられなかった。
自分がしでかしたことの重大さに一瞬、目の前が真っ白になった。
が、何もかもが終わったわけではない。
「救急車を…」
私は片野知美に向かって言った、つもりだった。
しかし、彼女もまた床に横たわっていた。
壁に頭だけもたれさせている。
短いスカートがめくれ、何も着けていない下半身が露わになっていた。
私は束の間、そこに目を奪われたが、すぐに片野知美の異変に気づいた。
大きな瞳を半分だけ開き、口元がだらしなく下がっていた。
そういえば、谷山修一を殴っている途中、止めに入った彼女を力任せに払いのけたような気がする。
私はその光景を思い出しながら、片野知美の美しい顔、口元に耳を近づけた。
呼吸がなかった。
首筋に手を当てるが、脈が停まっていた…。
私は恐慌をきたした。
なぜこんなことになってしまったのか、わからなかった。
不意に激烈な頭痛に襲われ、私は頭を両手で押さえた。
うめき声を漏らしながら、私は思った。
『彼らが行為をしていた事実を隠さなければならない』
私は恐ろしいほどの頭痛に耐えながら谷山修一の元へ行き、パンツとズボンを履かせ、カッターシャツの裾をズボンに入れてベルトを締めた。
頭痛が少し和らいだと思ったら、今度は身体が痒くなり始めた。
私は蕁麻疹の出た左の前腕部をかきながら、片野知美のところへ戻った。
片野知美を見下ろす。
谷山修一と片野知美は、私たちの理想である。
決して、彼と彼女が進んでそのような行為をしたという事実を残してはいけない。
私はベルトを外し、ズボンとパンツを下ろした。
驚くほどに屹立していた自らのそれをつかみ、床に両膝をついた。
片野知美の脚を持ち、中に押し入った。
温かい、そう思った途端に、私は頂点へたどり着いてしまった……。
放置されていた通学バッグから携帯電話を取り出し、119番と110番に電話をかけた。
そうしておいて、私は特別棟を後にした。
朝の空は、とても澄んでいるように感じられた。
私は空を仰ぎ、仰ぎつつ校内を歩いた。
雀の鳴き声が聞こえ、野球部の掛け声が遠くに聞こえた。
私は美しい世界を、そのまま保存しておきたかった。
限られた空間の中だけでもよかった。
願いはそれだけだった。
そう自らに言い聞かせた。
もう一度、空を仰ぐ。
頭痛は治まり、身体の痒みがなくなっていた。
【了】
この物語はフィクションです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【他の短編作品】









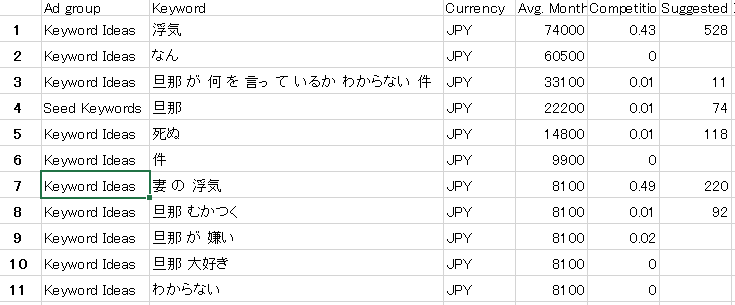
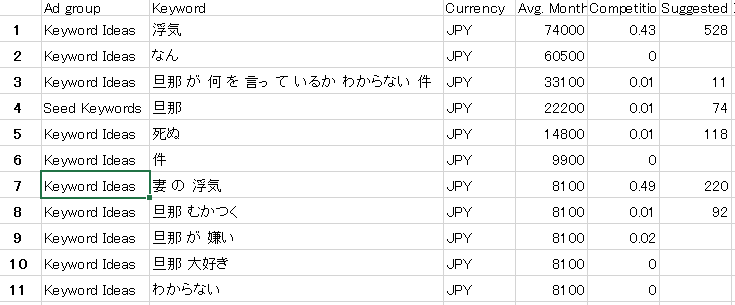
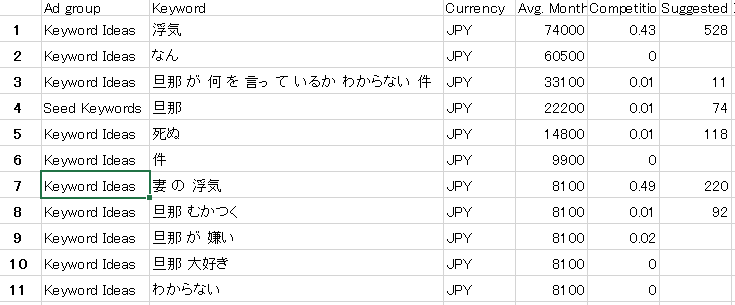








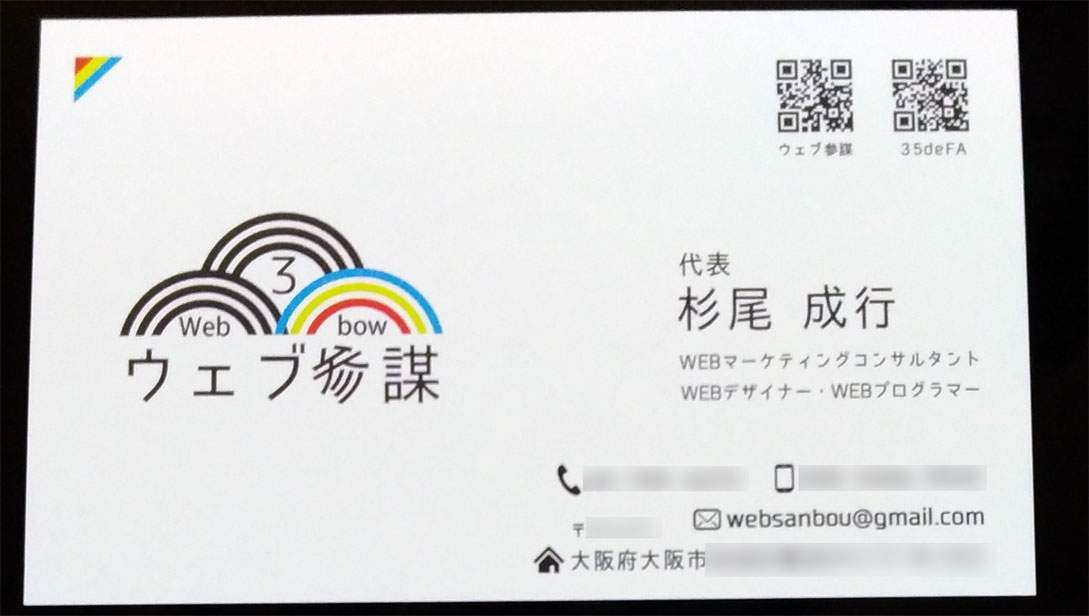


LEAVE A REPLY