読み切り短編小説 迷探偵『読了コンナン』 ~読者への挑戦状 君は最後まで読み切ることができるか~

※この瞬間、世界で最も無駄な時間を過ごしたくない方はこれ以上、読み進めないことをオススメします。
※もし読了した後、読んだ時間を返せと申されましても、私は全知全能の神でもなければ、タイムマシンを所持しているドラえもんでもないので補償はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
では本編をどうぞ。
迷探偵『読了コンナン』
「あばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばbbbbbbbばばぁあ」
僕は自分でも聞いたことがない声を上げたのだが、その理由は楽しみにとっておいた風呂上がりのカスタードプディングが冷蔵庫の中から消失していたためであり、そのことをもって精神に異常をきたしそうになったので、まあ落ち着けと自分に言い聞かせながら再度食べ物飲み物冷却便利装置内を覗いてみても、やはりそれは影も形もないのであった。
不可思議、奇々怪々、ミステリアス、奇怪千万という文字が、いわゆるマンモス校と言われる一学年に10クラス以上ある小学校の昼休みの校庭を駆け回る小学生のように頭の中を騒がしく駆け巡った。
僕がこのとき心に誓ったことをこの満天下に、大々的かつ大っぴらに発表させていただくことにしようと思いつつも、やはりこんなことを二十五歳にもなった大人が言っていいものか逡巡すること僅か0.5秒。
「僕のプディングを勝手に食べた犯人を必ず捜し出し、逮捕した上、人民裁判という名の私的裁判にかけ、できれば極刑に処してやりたいので、そやつには弁護士を絶対につけてやらないのだ」
何やら弁護士をつけないことが目的になったようにも見えるが、それは断固として違っていて、そう思った人がいたのなら僕の伝え方が間違っていたのであり、コミュニケーション不全ということが問題となりつつある世の中で僕がその一端を担ってしまったことを深く後悔し、自責の念を禁じ得ない。
ここで気づいたことは極刑とは何だということであり、通常のというか一般的に極刑と言うと死刑ということになるのだが、僕が個人的にそれをやってしまうとただの殺人で、あわよくばというか確実に僕自身が国家権力によって囚われの身となった挙句、いわゆる刑法という名の昔の人が作った法律によって裁かれる身となるのである。
ということは、僕はカスタードプディングを何者かによって食されたことにより、その個人的な憤懣を犯人と目した男ないしは女もしくは動物を弑することで晴らした結果、マスメディアやSNSによって個人情報を片っ端から洗いざらい暴露され拡散され、もしかしたら小学校のときに大便を漏らしながら廊下を歩いたことや、中学校のときに美代ちゃんに書いた今思えば憤死もののラブレターなんかも晒されることになりかねないのだ。
これは非常に割に合わないというか、メリットデメリットを天秤にかけてみてもとても釣り合う行為とは言えないと思いつつも、ここで僕が黙っていると、昨日から僕を冷蔵庫の中で待ちわびていた可愛いカスタードプディングちゃんの気持ちはどうなるのだと自分を奮い立たせた。
しかし、よく考えてみると、日本国の刑法における極刑が死刑なのであり、もしここが死刑廃止をした国、たとえば、の例が思いつかないが、勝手にフランスだとすると、極刑は多分終身刑あたりになるのだろうし、別の国ならもしかしたらもっと緩い刑罰があるのかもしれない。
そこで、このコンナン国において勝手にカスタードプディングを食べちゃった罪に対する刑罰を決めなければならない羽目に陥った僕の頭の中に、果たして立法権と司法権、更には行政権まで得てしまうと三権分立に反しているのではないかという疑問が浮かんだ。
ここは日本国でなく、かりそめの国、コンナン国なのだと強弁することが言葉の本当の意味で虚しいことに気づいた俊英かつ頭脳明晰な僕は、選挙も何もなく、そもそもお上が僕一人で、人民が誰であるかもわからない状態で思索をめぐらしてみても非常に不毛だという結論にたどり着いた。
「……よし、ならば捜査開始だ」
シンプルかつこれ以上ないほど合理的なことを言った僕の体が震えていたのは誰の目にも明らかだったと思うのだが、よくよく考えてみればこの狭い台所には僕以外誰もいないのだから、特に気にすることもなかった。
容疑者は居間にいる両親、父方の祖父母、それと二階の自室にこもってLINEなどというよくわからないコミュニケーションツールを用いて、彼氏という名のろくでなしと連絡をとっているであろう愚妹を合わせた五人だ。
この愚妹の彼氏である男は、自分の彼女である女の兄である僕に対してまともな挨拶すらできないどころか、顔を合わせた瞬間、噴き出すという失敬千万というか、およそ人とは思えない驚嘆すべき礼儀作法の持ち主であり、かつ男のくせにやけに身体が細く、更にそれを強調するようにスキニージーンズという名称の脚のラインを強調したズボンを履き、Tシャツの上にカーディガンとかいうお肌と自然に優しそうな素材のものを羽織り、やや長めの髪にパーマネントをあてて、実に不自然な方向に髪を遊ばせているロイド眼鏡の輩なのである。
こういう男がMacBook Airを携えて街を我が物顔で闊歩し、スターバックスもしくはサードウェーブコーヒー店のようなアメリカ被れ丸出しのカフェとかいう名の喫茶店に行き、アプリコットハニーソイクリームフラペチーノなどという初見では間違いなく言い淀んでしまうタイプの飲み物を頼んで、さも自分はオシャレに仕事をしていますという振りをしながらネットサーフィンをしてポルノ動画を漁っているのだと思うと、憤懣やる方なくなって我が国の行方を危ぶむ次第だ。
そもそも、おまえはそのポルノ動画をストレージに落としているのか、もし違うとしたら外付けHDDを使わずにどうしているのか、あれか今はやりのクラウド保存か、そんなことのために無料分では足りずに有料プランを契約しているのか、と小一時間問い詰めたいと思う気持ちを抑えながら、僕は台所を出た。
居間までの短い廊下を僕は怒りといういかんともしがたい感情を抑えるのに苦労したので、バックストレッチを走る競走馬のように優雅かつ躍動感溢れるフォームを意識することだけに集中して駆け抜けた。
たどり着いた居間という名の法廷で、僕という検察官兼裁判官は開口一番こう言った。
「あ、えっと、あの…。冷蔵庫の…」
「なんや、隆文かいな。どないしたんや」
温厚という表現がこれほど似合う人はいないと近所でも評判の祖父が目を丸くして言った。
「その、あ…、冷蔵庫に…」
「ああ、ご飯なら冷蔵庫やなくて、レンジの中に入れてあるで、チンして食べなさい」
いつもご飯を用意してくれる祖母の文子が、菩薩のような笑みを浮かべて優しい口調でそう言った。
「あ、そ…、いや、あの…。カスター…」
「何やの? はっきり言いなさい、あんたは」
鬼、もとい保険外交員をしている母が、帰ってきたばかりと思しきスーツ姿でコタツに入ってミカンを貪り食っている。
僕はその顔を直視できなかったので視線を斜め上に持っていくことで、心中を満たしかけた恐怖にも似た何か、いや、正直に言うと恐怖以外の何物でもない感情からも目をそらすことに成功した。
「何やの? はよ言いなさい」
「ぼ、僕、いや小生が先日購入してきたはずのカスタードプディングが、たった今、冷蔵庫の中を覗き見ると影も形もないといった風に消失しており、そのことにより小生が被った精神的ダメージはいかんともしがたいものであり…」
「は? プリンやろ? あんた、昨日の夜中、自分で食うてたで。覚えてへんのんかいな」
母の一言が僕に与えた衝撃の異常さは想像に難くないというか、とにかく甚大な痛みと打撃を受けた。
「そ、そんなはずはない、小生は風呂上がりにカスタードプディングを食べることのみに注力して本日をつつがなく過ごしてきたのであり、そのことをもって今日という日に区切りをつけて、また明日からの…」
「けったいな話し方しな。久しぶりに口きいたと思ったら。とにかく自分で食うてたわ。また自分の都合の悪い記憶を封じ込めて忘れてしまう変な癖が出てんねん。昔のことは覚えてんのに、最近の記憶が少ないという自覚はないのん?」
「あ、あばば…」
「せやから言うたやろ。ちゃんと病院行き、て」
「あ、あばばばば…」
「そんなことより、あんたいつから働くのん? いい加減、家にお金入れんと、外に放り出すで」
「良美さん、そない厳しいこと言わんと」
「おばあちゃんが甘やかすから、この子はいつまで経っても働かないんですよ。良い大学出て、ちゃんとした会社に入ったのにすぐに辞めて、それから一切働きもせんと毎日毎日部屋に閉じこもってパソコンいろうて。そもそも、あんた、偉そうに言うてるけど、そのプリンもおばあちゃんからもらったお小遣いで買うたんやろ。あたしが知らんとでも思うたら大間違いやで。情けないと思わへんの、大の男がお小遣いもろて買ったプリンを自分で食べておきながら、人のせいにして。そんなことやから、いつまで経っても就職できへん、彼女ができたこともない。はあ、いつになったらあたしは孫の顔が見れるんやろか。もう里美に期待するしかないかしらね。あの、こないだ連れてきた爽やかな二枚目の彼氏でいいわね。お父さんもそう思うやろ?」
「あばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばbbbbbbbばばぁあ」
【了】
※特定の個人を貶めるつもりで書いたものではありません。あらかじめご了承ください。
スポンサーリンク
【もう一記事いかがですか?】







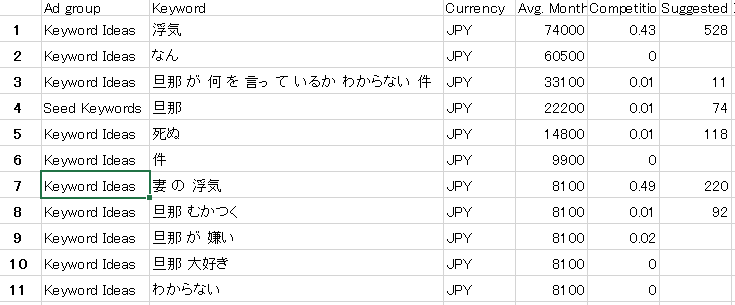
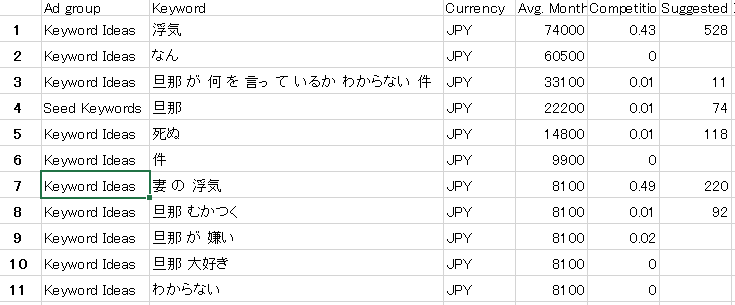
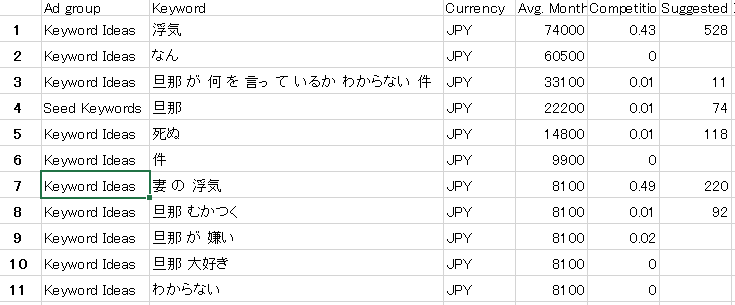







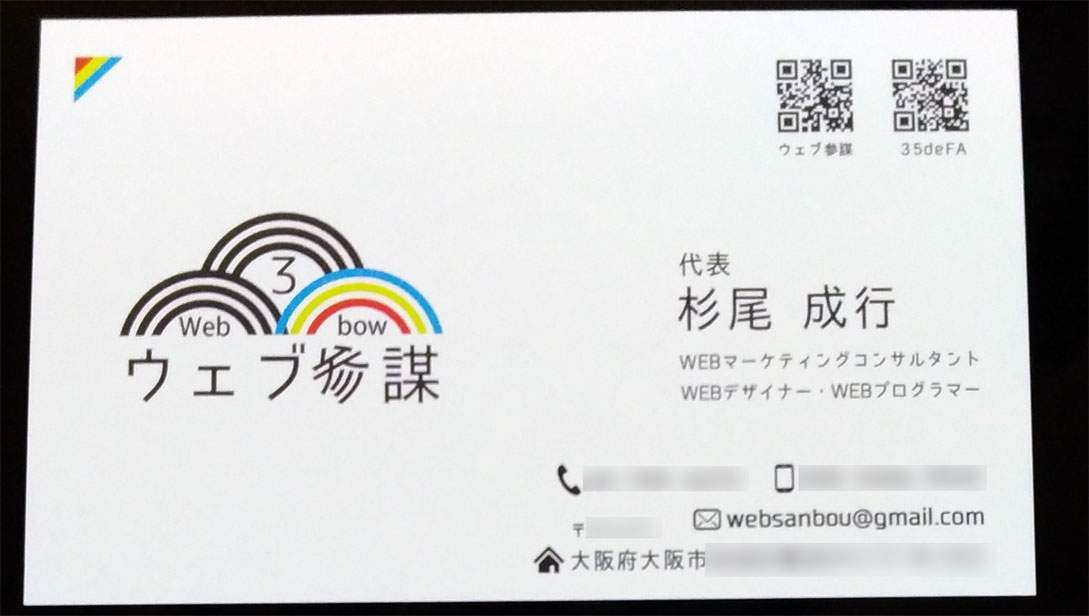



LEAVE A REPLY