【短編小説】浮気なん? 旦那と妻の浮気で嫌いと(以下、略) ~第三話

第一話はコチラ
⇒【短編小説】浮気なん? 旦那と妻の浮気で嫌いと大好きが交錯してむかつくけど、わからないので死ぬ寸前まで行った件 ~第一話
第二話はコチラ
⇒【短編小説】浮気なん? 旦那と妻の浮気で嫌いと大好きが(以下、略) ~第二話
サトシが車を降りた。
あたしは自分の息が荒くなるのを感じた。
それからラブホに入って部屋に着くまで、どこをどうやって歩いたのか覚えていない。
気づいたときには、サトシと手をつないで、部屋の中に入っていた。
背後で、部屋の鍵が自動で閉まった。
サトシに引っ張られながら、何とかミュールを脱ぎ捨てた。
「って、おいおいおい~。冗談でしょ!」
あたしは努めて明るい声で、サトシの背中に向かって言った。
にもかかわらず、サトシからは反応がない。
正直、あたしの心臓は爆発寸前だった。
サトシがゆっくりと振り返る。
「冗談なんかじゃねぇよ」
サトシがいつもより落ち着いた声で言った。
真顔だった。
「ちょいちょいちょい! らしくないって、マジで」
「なにが?」
「そんな顔。いや、だから、その、あのさ…」
「ちょっと黙れよ」
そう言ったサトシが、あたしの両腕を両手でつかんで上に引っ張り上げた。
あたしは中途半端に万歳するような格好になる。
あれっ? こいつって、こんなに背が高かったっけ?
そうか、ミュールの分…。
「あ」
あたしは壁に押し付けられる格好になった。
サトシが、顔が近づいてくる。
「ちょっ…」
寸前で顔を背けた。
「やなの?」
「え? いや、そんな…。じゃなくて…」
「じゃ、なんだよ?」
「やっぱり、ほら、ね」
「旦那さんのこと?」
サトシが顔を遠ざけて言った。
「え? いや…」
「まあ、そうだよな。人妻だもんな。仕方ねえよな」
サトシがあたしの腕を放した。
部屋の奥にある、やたらと大きなベッドに転がった。
「えっと…、あのさ…」
あたしはどう言えばいいかわからず、部屋の入口で立ち止まった。
「まあ、いいや。ちょっと休憩したら帰ろ。俺、今日、睡眠不足で、さ」
そう言って、サトシが身体を横向きにして向こうを向いた。
「あ、サトシ…」
あたしはベッドに座りながら言った。
返事はなかった。
聞こえたのは寝息の音だけだった。
しろよ、キス。
言えなかった。
その週の金曜日、旦那がいつもより早く帰宅した。
「あれ? 早いね」
ソファに座ってテレビを見ていたあたしは振り返って言った。
「ああ」
いつものように短く言って、旦那が書斎に入って行く。
あたしは、ご飯作らないとな、とぼんやり考えていた。
しばらくすると、旦那が書斎から出てきた。
ドアの音でわかった。
「ねえ、ご飯…」
そう言いかけたあたしの横を通り過ぎ、旦那がテレビ本体の電源を消した。
「ちょっと、何す…」
「話がある」
旦那が振り返って言った。
書斎に入って少し時間があったのに、旦那は服を着替えていなかった。
「え? 何?」
あたしは言った。
旦那は大きな茶封筒を手にしていた。
分厚い書類でも入っているのか、膨らんでいるように見える。
「何、それ?」
旦那が答えず、あたしの右斜め前のソファに腰を下ろした。
そして、茶封筒に手を突っ込んで、A4紙の束を取り出した。
「何、それ?」
あたしはもう一度、訊いた。
いつにない旦那の雰囲気に、嫌な予感しかしなかった。
「単刀直入に言うけど」
旦那がA4の紙束を見ながら言った。
「離婚しよう、俺たち」
「は? 意味わかんないし」
声が震えているような気がして、言い直した。
「意味わかんないし」
「わからないことはないと思うんだ」
「いや、意味わかんないし。ほんと、意味わかんない。そんなこと言われる覚えない」
「本当に? 君は心の底からそう言い切れる?」
「は? なに、それ。質問? 尋問? 不愉快なんですけど。マジ不愉快」
「これを見ても?」
旦那が再び茶封筒に手を突っ込んだ。
透明なビニールに包まれた大量の写真が出てきた。
「これ、君だよね」
旦那がビニールから写真を取り出す。
あたしだった。
あたしとサトシが、オープンカフェでお茶しているところが映っていた。
「君だよね。君と知らない男」
「知らない男じゃない。これはサトシ」
「へえ」
旦那が眼鏡の奥で、目を細めた。
「誰なの? お友達?」
「高校のときの親友。同じグループだった」
「グループって? 部活みたいなもの?」
「グループはグループだよ! 仲良しのグループ。あたしとユリとトーコとユキとアサミと…」
「ああ、そういうことね。結婚式に来てた子たち」
「それに男子も。サトシと…」
「名前はどうでもいいよ。今はそんな話してない」
「聞いたのはあんたでしょ!」
旦那は陰気な男だから、グループなんて言われてもわからないんだ。
この男は、学校でも一人で格好つけて、教室の隅の方で本を読んでいるようなタイプだ。
だからわからないんだ、グループって言われても。
「で、そのサトシ君と何したの?」
「お茶するくらいの何が悪いの?」
「お茶だけ?」
旦那がそう言って、次の写真をこちらに見せた。
そこにはイタリアンレストランに入って行くあたしとサトシが映っていた。
「ご飯も行った。だから何?」
「ご飯だけ?」
次の写真をこちらに見せる。
「映画館も行った。だから? あなた、連れて行ってくれなかったじゃん」
「映画、ねえ」
旦那が写真をめくった。
「ちょっとドライブしただけじゃん、サトシの車で」
「ドライブ?」
「サッカーも見に行ったわよ。それが…」
「その後に?」
旦那が次の写真をめくった。
サトシの車の後部が映っていた。
次の写真。
同じ構図だけど、背景が変わっている。
そして、次。
また車の後部。
次。
バイパスの降り口が映っていた。
「あ」
まさか、と思った。
旦那が次の写真をめくった。
サトシの車が、あのホテルに入って行くところが映っていた。
「だから、何?」
あたしは、写真から旦那の顔に視線を移して言った。
「何ってことはないんじゃないか?」
旦那が手を止めた。
「こんなの見せてきて、何のつもり? 感じ悪くない?」
「感じ悪い? それはどういう意味だろう? 僕の語彙にないな」
「あたしは気分を害しているって言ってんのよ」
「そうか。なら、僕が謝るよ。ごめん」
旦那が頭を下げた。
「何なのよ」
「でも、次は君が謝る番だ。謝ることに意味があるとは思えないが」
「な…」
あたしが言い終わる前に、旦那が写真をめくった。
ラブホテルの入り口から出てきた、あたしとサトシが映っていた。
正面やや右からの構図だった。
どうやって、こんなの。
どうやって、撮ったの?
誰かいたはずない。そんな記憶ない。
何、これ。何、これ。何、これ。何、これ…。
十回くらい口の中で繰り返した。
「か、隠し撮りじゃん、こんなの」
「だから、何?」
「ずるい、こんなの」
「ずるいかずるくないかは、この際、どうでも良くないか?」
旦那が言った。
「で、でも…」
「言いたいことはわかっている。その前に、これを見て」
旦那が写真をめくる。
あたしとサトシが出てきたホテルの入り口を撮った写真だった。
さっきの写真より少し距離をとり、ホテルの外観も入るようにしている。
「ここから、二人で出てきた。そうだね?」
「だから? だから、何? 何もしてないし」
「したかどうかは問題じゃないんだ。不倫関係にある男女2人が、この手の建物から出てきた時点でアウトなんだよ」
「ふ、不倫? ってか、してないし。何もなかったし」
「いや、そうじゃなくて。僕の話、聞いてたかな」
「してないから。キスもしてない。むしろよけたし」
「僕の話、聞いているかな?」
「してない、してない、してないし!」
「僕の話を聞け!!」
旦那が大声を出した。
そんな声を、初めて聞いた。
出せるんじゃん、大声。ずるいよ。
スポンサーリンク
「状況を整理しよう」
旦那が元の声に戻って言った。
天然パーマの髪の毛を一束、右手の人差し指と親指で巻き取っていた。
考えをまとめるときに、旦那がいつもする仕草だ。
ふと懐かしさを感じた。
久しく旦那と話していないことに気づいた…。
「いいかい。君は…」
「好きなの!」
言葉が、口を突いて出た。
「え?」
旦那がこちらを見て、止まった。
目が合った。
だけど、なぜだかその顔が滲んで見えた。
「あたし、好きなの、あなたが。ずっとずっと好きなの」
「今、僕が話しているのはそういう感情論ではなく…」
「感情以外に何を言えばいいのよ! 今更何を言えばいいのよ!」
頭の中が真っ白になり、身体が熱くなった。
何も考えられなかった。
「ちょっと待ってくれ。今、僕は…」
「あたしはあなたが好きなの。ずっとずっと前から」
「待っ…」
「待つ必要ある? 言う機会なんて、今しかないじゃない」
「一旦、落ち着こう。話ができない」
「話はしてるじゃない。今、この話を」
「違う。そうじゃない。このことを…」
旦那が写真を自分の顔の前に掲げた。
「じゃあ、聞かせて?」
あたしは写真を手で押し下げ、旦那の顔が見えるようにした。
滲んでいるけど、旦那の顔が近くにあった。
「な、何を?」
「あなたはあたしのこと、好き?」
「い、今更、何を…」
「あたしのこと好き?」
「好きとか、そういう…」
「好きかどうか聞いてるの。ねえ、どっち?」
「なぜ、その二択になるんだ」
「Yes or Noで答えられないの? そんなことも答えられないの? それでも学者先生なの?」
「僕は…」
旦那が目を逸らした。
「こっち見て言って、ほら」
あたしは旦那の顔を両手で挟んで、こっちを向かせた。
「僕は好きだなんて思っていない」
旦那がその手を払いのけて言った。
「好きだなんて思ったこともない!」
「は? 何言ってんの、おまえ?」
「え?」
「あたしを、好きと思ったことがないって? それ、本気で言ってんの?」
「いや、今はほら…。その話をしていないというか…」
「ああ、なるほど。死にたいんだ?」
あたしは台所に向かった。
シンクの下のドアを開け、磨き上げた包丁を取り出した。
なにせあたしは、料理は嫌いだけど、包丁を研ぐのは好きだから。
包丁を研いでいると、なぜか心が落ち着くから。
落ち着くの、包丁大好き。
「ま、待て。何をしてるんだ」
旦那がソファから立ちあがった。
「え? 死にたいんでしょ? そうだよね?」
「ち、違う。今、僕たちが話すべきは…」
「じゃあ、答えて?」
あたしは包丁を正眼に構えながら一歩踏み出して言った。
「な、なにを?」
「あたしのこと、好き?」
束の間、そこには静寂があった。
「嫌いだ! 君のこと、嫌いだ!」
「きょえ~~~~~~!!」
四歩で到達した。
旦那のところに。
包丁を振り上げた。
が、旦那の次の動きは想定になかった。
踏み込んできた。
しかも、低い体勢で。
タックル。
まともに腹に受けた。
気づいたときには、床に横たわっていた。
懐かしい匂いがした。
あたしは目を開けた。
旦那が覆いかぶさるように倒れていた。
ちょうど胸のところにある顔を両手で挟んだ。
「なんだか、懐かしい」
あたしはそう言った。
が、返ってきた言葉は思ってもみないものだった。
「やめろ、気持ち悪い!」
旦那があたしの手を振り払って、立ち上がった。
気持ち悪い? 気持ちわるい? きもちわるい? キモチワルイ?
意味がわかったとき、あたしは立ち上がった。
「わかった。あたし、死ぬ」
車のキーをキッチンカウンターから取って玄関に向かって走り出した。
「おい!」
呼びかける声が聞こえたような気がした。
気がしただけかもしれなかった。



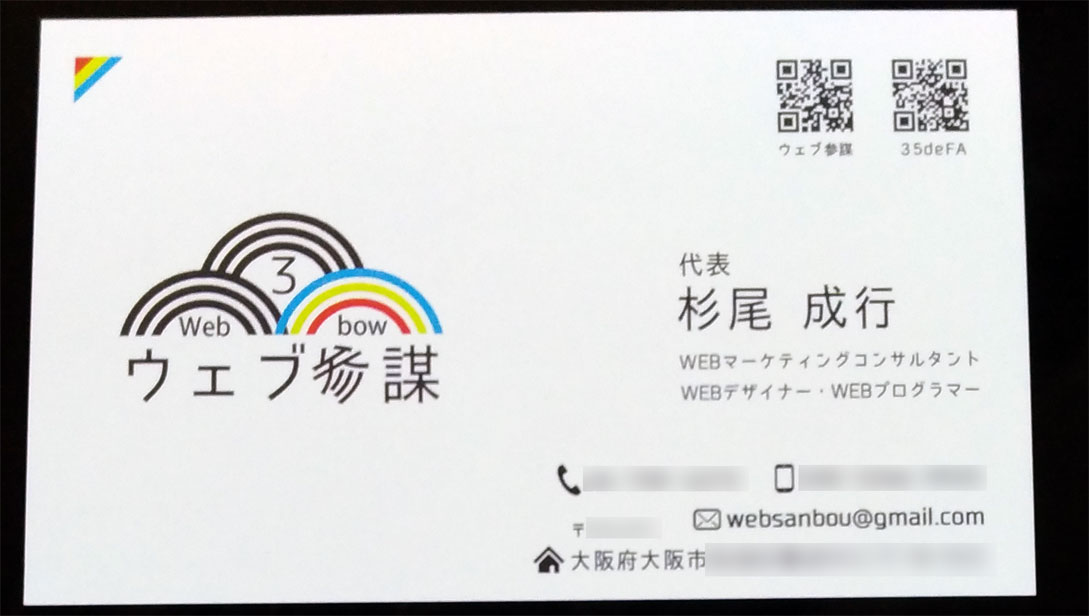



LEAVE A REPLY