ウェブ狼 第七話 ~容認~

「あの後、お連れの人を尾けました」
瞳が言った。
「ってことは、俺らが出てくるのを待ってたんか」
長居しなかったとはいえ、そのバーに一時間はいたはずだ。
「昼だったら暑くて無理でしょうけど、お酒も飲んでたし平気でしたよ」
「ちゃう。あんなところに一時間も突っ立ってたんか。そう言うてんねん」
御堂筋の程近くだから、人通りがないわけではない。
しかし、終電もなくなろうという時間だ。
若い女が一人でいていい場所ではない。
「しかも、俺じゃなくて奴をつけたって?」
「そうですけど」
瞳が真っ直ぐこっちを見て言った。
「まあ、それはええわ。で、奴はどこへ行った?」
「その前に、あの人がどういう人なのか教えてください」
「君はどう思う?」
「まともな人間じゃないと思いました。そんな人と付き合っている先輩のことがわからなくなりました。でも…」
「でも?」
「そこで気づいたんです。あの人と仕事をしているんだったら辻褄が合うって。でも、あんなクライアントさんは見たことないから…」
「だから俺が副業をしていると思った?」
「はい」
瞳が頷いた。
「君がそう思うなら、そういうことなんやろう」
「違うんですか」
「今、質問してるのは俺やで。奴はどこへ行った?」
「いかがわしいお店がいっぱいのビルに」
瞳が顔を歪めて言った。
「あたしは入れないから、帰りました。どっちにしろ、まともな人間じゃないと思います」
「おいおい、キャバクラや風俗店に行ったら、まともな人間とちゃうんか」
「先輩も行くんですか」
「俺が行くかどうかは別の話や」
「行くんですか、どうなんですか」
瞳が語気を強めた。
「キャバクラは付き合いで行くことがある。それは同伴者が喜んでくれるからや。でも、風俗店は行かない。そんな暇があったら息子の顔が見たい」
「そうですか。だったらいいんです」
瞳がうつむいて言った。
道徳的にどうかは別として、男が酔っぱらって風俗店に行くのは不思議なことではない。
だから、その一事をもって、まともな人間でないと断じるのは早計だと思う。
とはいえ、そんな議論をするのは不毛だし、今すべきことではない。
「で、君は、俺が副業しているとして、それをどうするつもりなんや」
「あたしもその副業に参加させてください」
「なぜ?」
ミソジは短く言った。
「面白そうだからです」
「それが理由?」
「それに、色々と勉強になることがあるでしょうし」
瞳が目を輝かせて言った。
「なるほど」
「迷惑ですか」
瞳がこちらを窺うようにして言った。
「引き寄せの法則って知ってるか」
瞳の質問に答えずに、ミソジは問いかけた。
「聞いたことはあります」
「ものすごく単純化して説明すると、考えていること興味があることを引き寄せるってことやねん」
「ええ、それが?」
「君もそんなもんに興味持ってたら、余計なこと、知らんでええことにまで首を突っ込まなあかんことになるで」
「知らなくていいことって何ですか」
「親御さんに心配かけることになりかねない。そういうことを言うてるんや」
「親は関係ありません」
「そういえば関西弁ちゃうな。出身はどこやったっけ?」
「・・・北海道です」
「えらい遠くまで来てるねんな」
「別にいいじゃないですか」
「悪いとは言うてへん。でも、遠くにいるご両親に…」
「母はいません。あたしが中学生のときに亡くなりました。心筋梗塞で」
「それはすまなかった。でも、お父さんだけなら尚更…」
「先輩」
瞳が途中で話を遮った。
「なんや?」
「家庭事情は関係ありません。あたしはもう大人です。それに…」
瞳が言いよどんだ。
「それに?」
ミソジは促すように言った。
瞳の表情、仕草から、出かけた言葉に何らかの感情がこもっていることを感じ取ったからだ。
「・・・父とは折り合いが悪いんです」
「なるほど」
ミソジは自分が柄にもなく説教していることに気づいた。
家庭云々の話はどうでもよかった。
ただ説得の材料に使っているだけだった。
そして、そのことが彼女を侮辱しているということに気づいた。
最近の若い子は何より家族を大事にする。
女の子なら尚更だろうというレッテル貼り、カテゴライズ。
自分の悪い癖だ。
スポンサーリンク
「まあ、理由はどうあれ、あかんわ」
「え~、なんでですか」
瞳が、間の抜けたともとれる声を上げた。
「第一に、俺は副業をやっていない。第二に、仮にやっていたとして、君を引き入れることはしない」
「どうしてですか」
「答えはシンプル。君に働いてもらう。支払いをする。そうすると俺の取り分が減る」
「嘘つき」
「どこが?」
「じゃあ、さっきなんであたしの両親のこと言ったんですか」
「それは、やな。君の将来のことを思って…」
「先輩、動揺してますよ」
「してへんわ」
「いや、してます。右頬がちょっと上がってますもん」
「なんや、それ」
「クセですよ、先輩の。感情が動いたときに出ます。たとえば、イライラしたときとか」
「そうかな」
言われて気づいたが、確かにそうかもしれない。ミソジは思った。
「そんなことどうしてわかる?」
「あたし、大学で心理学を専攻してましたから」
「なるほど」
「それもクセですよ。『なるほど』って言うの。そう言いながら考え事してる」
「俺を分析せんといてくれ」
ミソジは苦笑して言った。
彼女の言う通り、一緒に仕事をしたら面白いかもしれない。
そう思ってしまった自分を、心中で否定していた。
自分は大人っぽい女性が好みだ。
目の前にいる女は、身体こそ発育しているが、顔立ちが幼い上に中身も子どもだ。
言い訳を探して出てきたのは、その程度のことだった。
「わかった。参加させよう。でも、この件は他言無用やで」
ミソジは自分の口を突いて出た言葉に驚いた。
ほんの数十秒前に考えていたことと真逆の決定だった。
「本当ですか? 吐いた唾は呑まないでくださいよ」
瞳が身を乗り出した。
「どこで覚えた? そんな言葉」
「Vシネマです」
瞳が屈託のない笑顔で言った。



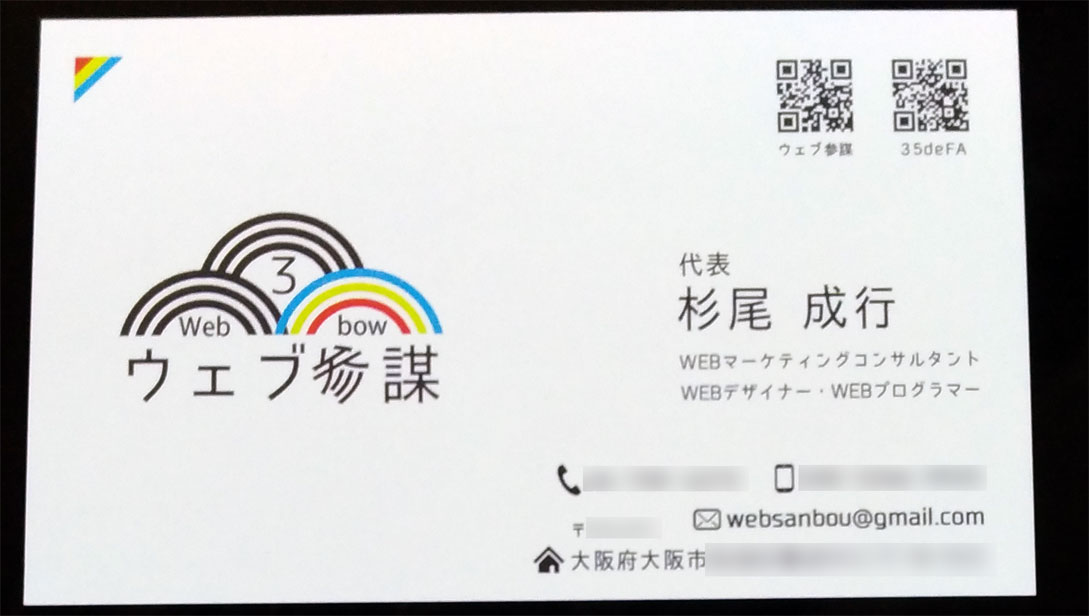




LEAVE A REPLY